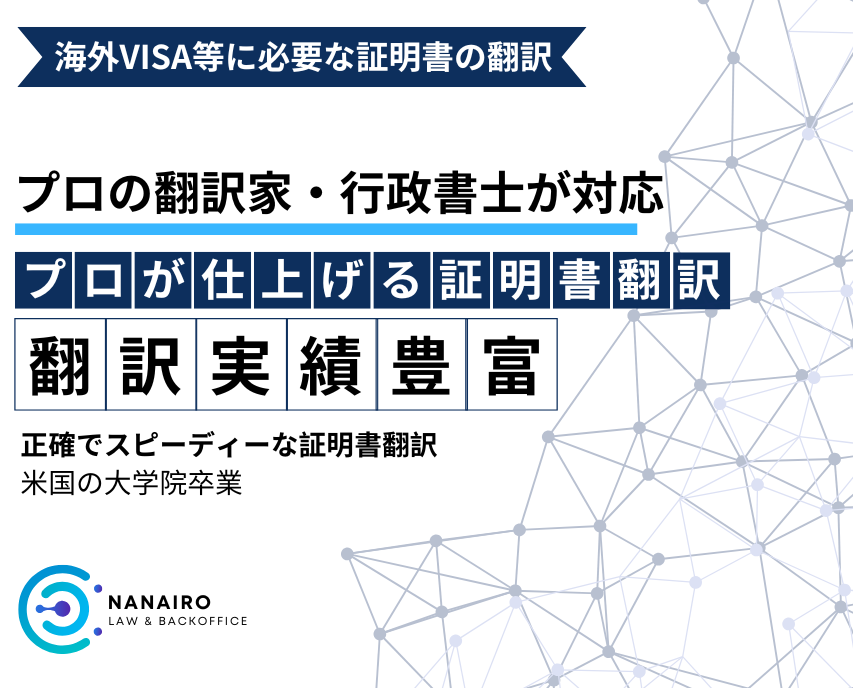住民票の英語翻訳(英訳)は自分でできる?依頼方法と注意点を行政書士が解説
【2025年11月14日作成】
海外赴任・留学・ワーキングホリデー・国際結婚・海外でのビザ申請など、 海外と関わるライフイベントの増加に伴い、「住民票の英語翻訳が必要です」と案内されるケースがあります。 住民票は、住所や氏名、世帯構成などを公式に証明する公的書類であり、 海外の行政機関・教育機関・金融機関でも、本人確認や住所証明として提出を求められることが多いからです。
ところが、日本の市区町村では原則として住民票の「英語版」は発行していません。 そのため、英訳が必要になったときには、「自分で翻訳する」か「翻訳会社や行政書士などの専門家に依頼する」必要があります。
初めて英訳を求められた方にとっては、 「自力で翻訳してもいいのか」「どんな形式なら受理されるのか」「翻訳証明とは何か」など、 分からない点が多く、不安も大きいと思います。 本記事では、実務と証明書翻訳に携わってきた行政書士の視点から、 住民票の英訳が必要になる場面、自力翻訳の可否とリスク、 専門家へ依頼する際の流れや費用感まで、分かりやすく整理して解説します。

目次
1. 住民票の英訳が必要になる典型的なケース
住民票の英訳が求められる場面として、代表的なものは次のようなケースです。
- 海外赴任や駐在員としての渡航時の在留手続き
- 海外大学・語学学校への留学・ワーキングホリデー
- 配偶者ビザ・家族滞在ビザなどの海外でのビザ申請
- 海外の銀行口座開設やクレジットカード申請
- 海外での賃貸契約や携帯電話契約時の住所確認
日本では運転免許証やマイナンバーカードなどが身分証明として使われますが、 海外ではこれらがそのまま通用しないケースも多く、 「公的機関が発行した住民登録の証明書」として住民票の提出を求められることがあります。
その一方で、前述のとおり市区町村では住民票の英語版は発行していません。 したがって、原本(日本語)を取得したうえで、別途英訳を用意する必要があります。
2. 住民票の英訳は自分でできる?自力翻訳の可否と注意点
結論から言うと、住民票の英訳を「自分で作ること自体」は禁止されていません。 英語が得意な方であれば、項目ごとの内容を書き写す作業そのものは可能です。
ただし、より重要なのは「自分で翻訳したものを提出先が認めるかどうか」という点です。 特にビザや永住権申請などの手続きでは、次のような条件が課されていることがあります。
- 翻訳文に翻訳者の署名が必要(Translator's Signature)
- 翻訳者の氏名・住所・連絡先の記載が必要
- 翻訳者が「本人以外の第三者」であること
- 翻訳証明書(Certificate of Translation)の添付が必須とされている
本人による翻訳は「客観性がない」と判断されやすく、 受理されないケースも少なくありません。 特にアメリカやカナダ向けの手続きでは、 「第三者による翻訳+翻訳証明」が事実上必須となっていることが多く、 自力翻訳は現実的でない場合も多い点に注意が必要です。
3. 英訳の際に必ず翻訳すべき項目
住民票のレイアウトは自治体によって多少異なりますが、 英訳の際には、少なくとも次の項目を正確に翻訳する必要があります。
氏名(Name)
パスポートに記載されているローマ字表記と完全に一致させることが重要です。 綴りや姓名の順序が異なると、同一人物として扱ってもらえない場合があります。
生年月日(Date of Birth)
西暦表記とし、月は January / February などの英語表記を用いるのが一般的です。
住所(Address)
日本の住所を英語表記にする際には、 番地・丁目・町名・市区町村・都道府県の順序を適切に並べ替える必要があります。 住民票に記載されている所在地と対応するように、正確な英訳を行います。
世帯主氏名・続柄(Head of Household / Relationship)
「続柄」は誤訳されやすい項目です。代表的な訳語は次のとおりです。
- 世帯主:Head of Household
- 父:Father
- 母:Mother
- 妻:Wife
- 夫:Husband
- 子:Son / Daughter
国籍・在留資格(Nationality / Status of Residence)
記載がある場合は、そのまま正確に翻訳します。 ビザ申請では重要な情報となることが多いため、誤訳は禁物です。
マイナンバーに関する注意点(Individual Number)
住民票にマイナンバーが記載されている場合でも、提出先が求めない限り、 原則として個人番号の記載がない住民票を取得することをおすすめします。 不要な個人情報の開示を避ける観点からも、安全性の高い選択肢です。
4. レイアウト再現が重要な理由と作成のポイント
住民票の英訳で見落とされがちですが、とても重要なのが「原本のレイアウトをできる限り忠実に再現すること」です。
海外の担当者は日本語を読めないことが多く、 「どの項目がどの翻訳と対応しているか」が一目で分からないと、 「必要な情報が抜けている」と判断されてしまう可能性があります。
自力で作成する場合は、エクセルやGoogle Sheetsで表を作り、 項目名と内容を一つ一つ対応させていく方法が扱いやすいでしょう。 なないろバックオフィスでは、Google Sheetsを使用します。
5. 自力翻訳で起こりやすいトラブルと提出先のチェック基準
自分で住民票を翻訳した場合、次のようなトラブルが頻繁に発生します。
① レイアウトや項目抜けによる差し戻し
原本にある項目が翻訳に含まれていなかったり、 項目の対応関係が分かりづらかったりすると、 「必要な情報が記載されていない」と判断され差し戻されることがあります。
② 続柄・住所表記の誤訳による再提出
続柄の誤訳や、住所の番地・号の並び替えミスなど、 一見小さなミスでも、審査側にとっては大きな問題となり得ます。
③ 翻訳証明(Translator's Certificate)の不足
多くの国では、単なる「英訳文」ではなく、 翻訳者が「原本の内容を正確かつ完全に翻訳したことを証明する文書」を求めています。 本人が自分で翻訳した場合、この証明の客観性が弱く、受理されないケースがあります。
6. 行政書士・翻訳専門家に依頼するメリット
住民票の英訳は、単なる英文翻訳ではなく、 公的書類として海外の行政機関等に提出するための書類作成です。 この点を踏まえると、行政書士に依頼するメリットは大きく、 特に次のような点で安心感が違います。
- 原本レイアウトを踏まえた見やすい翻訳書式の作成
- 続柄・住所・在留資格など専門的な用語の正確な英訳
- 提出先の要件に沿った翻訳証明(Certificate of Translation)の付与
なないろバックオフィスは、民亊法務の経験が豊富な行政書士に加え、米国の大学院卒で翻訳実務の経験も豊富な行政書士(TOEIC925点)が在籍、2名体制で全ての翻訳を監修しています。 誤訳や記載漏れがないように注意しながら、 海外提出に耐えうる品質の住民票英訳を提供しています。
7. 行政書士に住民票英訳を依頼する流れ
住民票の英訳を行政書士に依頼する場合、基本的な流れは次のとおりです。
- 住民票原本の取得
コンビニ交付や市区町村窓口で、最新の住民票を取得します。 個人番号が不要な場合は、マイナンバー記載なしの住民票を選択します。 - 住民票の画像またはPDFを送付
スマホで撮影した写真やスキャンデータを、メールやLINE等でお送りいただきます。 - 英訳文の作成
原本のレイアウトに沿った表形式で英訳を作成し、内容の整合性を確認します。 - 翻訳証明書の作成(必要に応じて)
提出先が翻訳証明を求めている場合、Certificate of Translation を発行します。 - PDFで納品
通常はPDFで納品し、そのままオンライン申請やプリントアウトでご利用いただけます。 原本郵送が必要な場合には、別途ご相談のうえ対応します。
海外在住の方からのご依頼でも、PDFベースで完結できるため、 「日本に住んでいないから依頼しづらい」という心配は不要です。
8. 住民票の英訳料金と翻訳証明について(なないろバックオフィスの場合)
当事務所では、戸籍謄本・抄本の英訳と同じ体系で、 住民票の英訳にも分かりやすい料金設定を採用しています。
● 住民票の英訳料金
住民票 1枚:4,500円(税抜き)
翻訳証明書(Certificate of Translation):3,000円(税抜き)
※当事務所の行政書士名で発行します。電子署名または押印で対応可能です。
行政書士2名体制でダブルチェックを行い、 公的手続きに耐えうる品質の英訳と翻訳証明をセットでご提供しています。 納期の目安は、通常ご依頼から最短即日〜翌営業日程度ですが、お急ぎの場合は事前にご相談ください。
なないろバックオフィスの証明書翻訳は こちら
9. まとめ|「形式」と「正確さ」を両立した住民票英訳を
住民票の英語翻訳は、自分で作成すること自体は可能ですが、 実際には「提出先がそれを正式な書類として認めてくれるかどうか」が重要なポイントです。 とくにビザや永住権、海外の行政手続きでは、 レイアウトや翻訳精度だけでなく、翻訳証明の有無が結果を左右することもあります。
なないろバックオフィスでは、行政書士2名体制で住民票の英訳・翻訳証明に対応しており、 原本レイアウトを踏まえた分かりやすい書式と、公的手続きに耐えうる正確な翻訳をご提供しています。 「自分でやってみたけれど不安」「1回で確実に通したい」という方は、 ぜひ一度お気軽にご相談ください。 LINE・お問い合わせフォーム・お電話から、初回無料でご相談いただけます。
提携先:行政書士藤原七海事務所
今すぐ相談(全国対応、無料相談、土日歓迎)

行政書士
基本情報技術者
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori
LINE / Zoom(全国対応、無料相談、土日祝日可)
LINEでの問い合わせはこちらのQRより